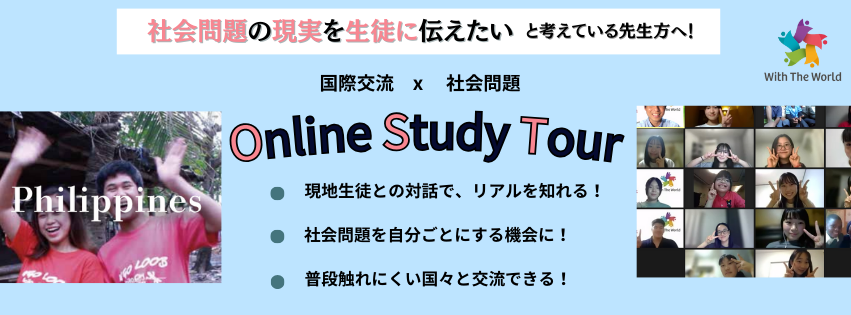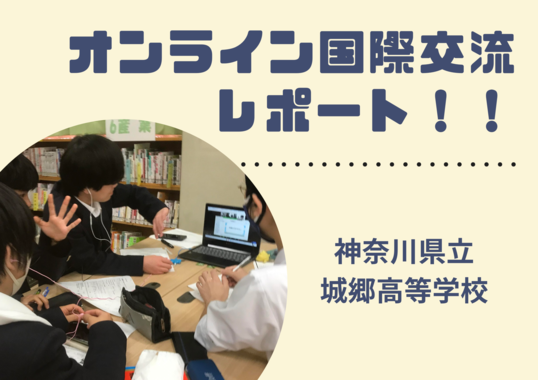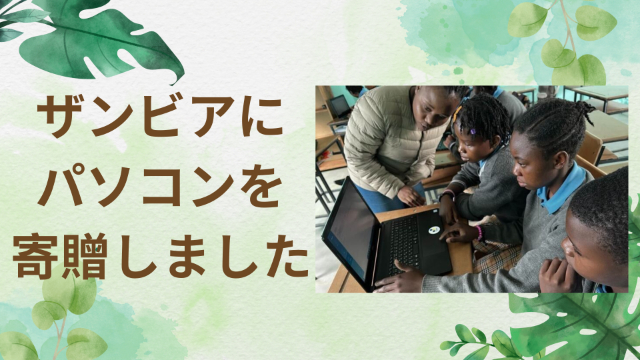平和学習のテーマと事例紹介〜戦後80年、平和をどう伝えるか〜

戦後80年 平和学習をどう行うか
1945年8月15日の終戦から80年の節目を迎える今年。戦争を経験したことのある人が少なってきている現在、歴史の継承の難しさが話題にあがることも多々あります。教育現場では、いかにして平和を築く力をもった子どもたちを育てていくのかが課題となっています。
この記事では、新たな平和学習の実践例を紹介していきます。
探究学習×平和学習の事例紹介
・長崎市の事例:事前に長崎について学び、「平和のためにできること」をディスカッション
長崎県では、長崎S D G平和ワークショップが行われています。生徒たちは、オンラインで事前学習として長崎の歴史を学んだのち、平和ガイドとの被爆遺構めぐりや原爆資料館見学を行います。その後、平和推進の取り組みやその課題についてレクチャーを受けたのち、「平和を実現するために、自分たちに何ができるか」について、グループごとに発表や意見交換を行なっていきます。
【参考】長崎市公式サイト Travel Nagasaki
https://www.at-nagasaki.jp/education/article/sdgs
【参考】日本修学旅行協会 進化した長崎市の「長崎SDGs平和ワークショップ」と体験・探究型教育旅行プログラム
https://jstb.or.jp/pages/173/detail=1/b_id=1487/r_id=9/
・「ラスト10フィート」プロジェクト:広島を訪れた外国人に戦争や平和についてインタビューを行う
広島の平和資料館で行われた、教育学の視点から戦争と平和の意味を問い直す「ラスト10フィート」プロジェクトでは、広島の平和資料館を訪れた外国人にインタビューを行いました。自分たちが展示の作り手ー語り手となる経験を通し、能動的に平和学習の学びを得ていく取り組みが行われています。
【参考】日本教育新聞 受け身から発信へ、「平和学習」を変える
https://www.kyoiku-press.com/post-296770/
世界の同年代から平和について学ぶ。ともに、平和について語り合う
探究学習の平和教育に加え、世界の同年代から平和・戦争について学ぶ取り組みも行われています。同年代の若者とともに学んでいくことで、自分自身に関わりのあることとして、平和について考えていくことが期待されます。
松蔭中学校・高等学校では、2024年まで内戦が続いたシリアの学生とオンラインで繋がり、戦争と平和について語り合う平和学習が実施されました。
本プログラムでは、生徒たちはシリアの「今」と「昔」に焦点を当て、シリアのリアルな現状について学んでいきます。現地の幼稚園や大学の視察を行ったり、現地に住む戦争を経験した同年代の若者たちから、シリアの現在の様子や歴史、文化などについて対話を行っていきました。
また、シリアの子供たちへ教育支援や日本国内での平和養育活動を行っているNPO法人「Piece of Syria」の代表中野さんによる、シリアの現状や課題といったシリアの「今」についてのパネルディスカッションや、「シリアの今と昔」というテーマの映像を視聴通し、シリアの歴史や現状に対する理解を深めていきました。

戦後80年を迎える、今。With The Worldは生徒の心に残り、将来につながる力を育てゆくため、新たな平和学習のあり方を模索・提案してきます。
↓世界の同年代とともに、社会課題を学ぶ「オンラインスタディツアー」。詳細はこちら